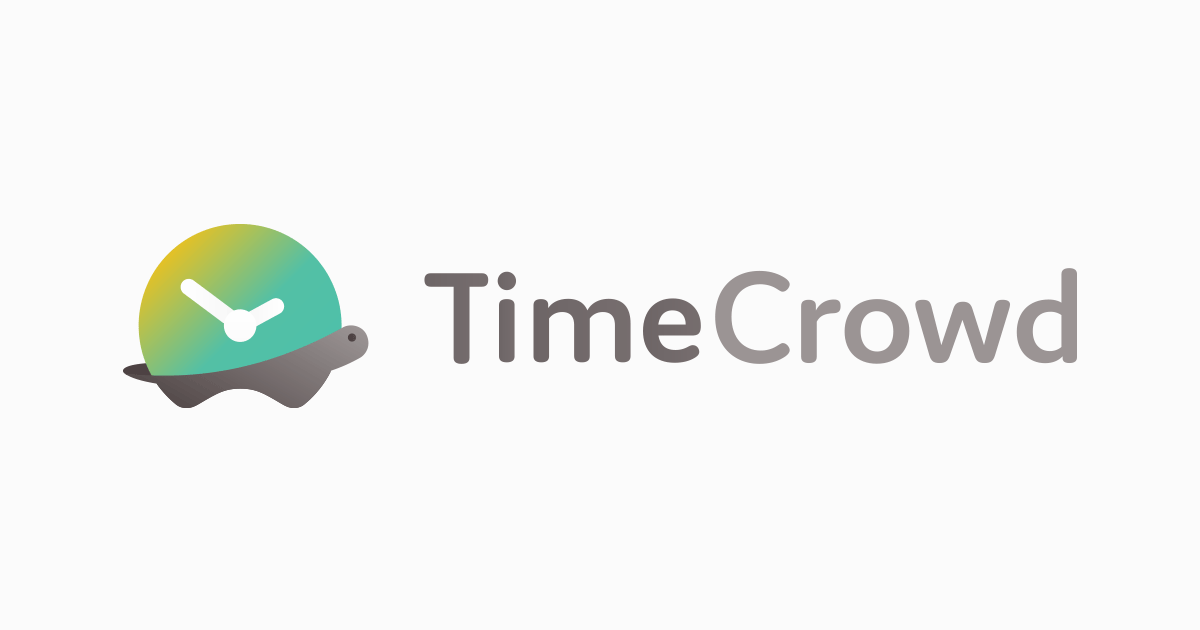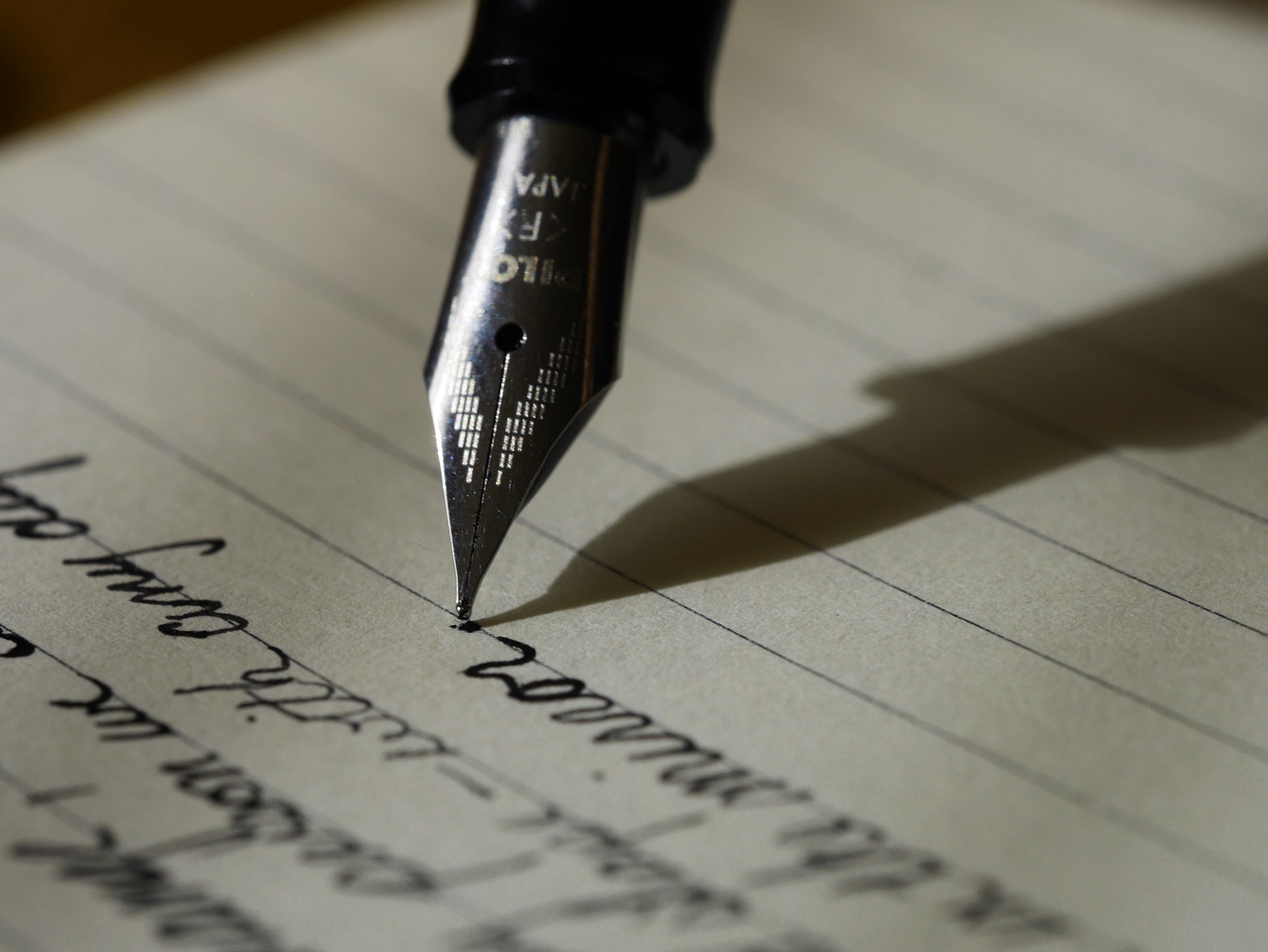「今月の経理シェアードサービスの原価、把握できていますか?」
この問いに即答できる企業は、決して多くありません。複数の事業部門を支援するシェアードサービスでは、誰が、どの部門の業務に、どれだけの時間を費やしたのか——その実態が見えづらいという構造的な課題を抱えています。原価が見えなければ、採算性の評価はできません。適正な内部請求額も設定できません。そして何より、現場で働く従業員の努力が、正当に評価されることもないのです。
目次
シェアードサービスが抱える「見えない原価」の問題
複数部門への対応で分散する工数
経理シェアードサービスで働くAさんの、ある一日を見てみましょう。
- 午前:東日本事業部の経費精算処理(2時間)
- 午後前半:西日本事業部の月次決算サポート(1.5時間)
- 午後後半:海外事業部の送金処理(1時間)
- 夕方:全社会議への参加(0.5時間)
Aさんの人件費は、月額40万円です。この日の労働時間5時間を、各事業部にどう配賦すべきでしょうか。
単純に「3部門で割る」では、実態から乖離します。しかし、多くのシェアードサービスでは、こうした「感覚」や「大まかな按分」で原価を算出しているのが実情ではないでしょうか。
見えない原価がもたらす経営リスク
工数が可視化されていない状況では、以下のような問題が静かに進行します。
採算性の誤認
実際には赤字の案件を、黒字だと誤認したまま継続してしまう。特定部門への過度なリソース投下に気づけない。
不適切な価格設定
内部請求額(仕切り率)の根拠が曖昧なまま、「前年踏襲」や「なんとなく」で設定される。市場相場との乖離にも気づきにくい。
説明責任の欠如
依頼元部門から「なぜこの金額なのか」と問われても、客観的なデータで説明できない。信頼関係の構築が困難になる。
人的稼働が原価の大部分を占めるビジネスモデルにおいて、売上を上回る人件費の投下は即座に赤字案件となります。この構造的な問題が積み重なれば、企業の収益性を大きく損ない、場合によっては事業継続そのものが危ぶまれる事態にも発展しかねません。
工数管理が実現する原価の可視化
ステップ1:部門別・業務別の工数を記録する
TimeCrowdのようなタイムトラッキングツールを使えば、日々の業務を記録する習慣を作ることができます。
記録例
- プロジェクト:東日本事業部
タスク:経費精算処理(2時間) - プロジェクト:西日本事業部
タスク:月次決算サポート(1.5時間) - プロジェクト:海外事業部
タスク:送金処理(1時間)
この記録を1ヶ月続けるだけで、「どの部門に何時間使ったか」が自動的に集計されます。
ステップ2:工数から原価を計算する
工数データが蓄積されたら、次は原価計算です。
計算式
部門別原価 = その部門向け工数 × 人件費単価
具体例
- Aさんの人件費単価:4,000円/時間
- 東日本事業部向け工数:40時間/月
- 東日本事業部の原価:160,000円/月
チーム全体で集計すれば、各部門に対する真のコストが明確になります。
ステップ3:採算性を評価する
原価が見えれば、現在の仕切り率(内部請求金額)が適切かどうかを判断できます。
評価例
- 東日本事業部への請求額:月額20万円
- 実際の原価:月額16万円
- 利益率:20% → 適正範囲
もし原価が請求額を上回っていれば、業務プロセスの見直しや仕切り率の調整を検討する材料になります。
なぜシェアードサービスにTimeCrowdが適しているのか
1. 複数部門対応の実態をそのまま記録できる
プロジェクト機能を使えば、依頼元部門ごとに工数を分けて記録可能。複雑な按分計算も不要で、実態をそのまま可視化できます。
2. 定型業務の標準工数が見えてくる
「月次決算」「給与計算」「採用面接」など、繰り返し発生する業務の工数を蓄積することで、標準工数が明確になります。これは業務改善やBPO検討の重要な判断材料です。
活用例
「給与計算の標準工数は5時間/月」というデータがあれば、外注見積もり(7万円)との比較が可能。社内コスト(5時間×4,000円=2万円)の方が有利→内製継続の判断ができます。
3. 繁閑差を可視化し、リソース配分を最適化
過去の工数データから、「月末は通常週の1.5倍の工数がかかる」といった傾向が見えてきます。これにより、事前の応援体制構築や残業予測が可能になります。
4. 依頼元部門への説明責任を果たせる
「今月は想定より工数がかかりました」という説明も、実際の工数データがあれば説得力が増します。依頼元との信頼関係構築にもつながります。
数値の裏側にある真実——従業員を守る視点
原価管理における工数データは、単なる数値以上の意味を持ちます。従業員がある案件にどれだけ真摯に向き合っているか。仮に予算を超過する工数が発生していたとしても、その事実だけで評価を下すことはできません。
重要なのは、「なぜ、どの業務に時間を要しているのか」を丁寧に分析することです。「パフォーマンスが低い」という一言で片付けるのは、あまりにも短絡的です。案件が難航している真因を突き止め、発注側の要求や業務プロセスに問題があるならば、そこにメスを入れる必要があります。
TimeCrowdの重要な役割——
それは「従業員を守る」ことです。
時には、発注金額そのものが市場相場や実態と乖離しているケースも見受けられます。そうした局面では、正確な時間データが価格交渉の強力な根拠となります。感覚や経験則ではなく、客観的なファクトに基づいた対話が可能になることで、適正な取引条件の実現につながるのです。
導入の第一歩:小さく始めて習慣化する
いきなり全業務の工数記録は大変です。まずは以下のステップで始めることをお勧めします。
フェーズ1:主要業務から記録開始(1ヶ月)
- 月次決算、給与計算など、時間のかかる主要業務のみ記録
- 「完璧」を目指さず、「70%の精度」で継続することを優先
フェーズ2:全業務に拡大(2〜3ヶ月目)
- 記録習慣が定着したら、全ての業務を記録対象に
- 週次でチーム内レビューを実施し、記録漏れを防ぐ
フェーズ3:データ活用開始(3ヶ月目以降)
- 蓄積データから部門別原価を算出
- 標準工数の設定、繁忙期予測などに活用
- 経営層への報告資料として活用
ミッション「生きた時間を増やす」の実現
TimeCrowd株式会社は、「生きた時間を増やす」というミッションを掲げています。
従業員が費やす時間を、ただの労働時間として消費するのではなく、一人ひとりが誇りを持って取り組んだ成果として評価されるべきもの——私たちはそう考えています。その実現のためには、時間の可視化が不可欠です。
シェアードサービスにおける原価管理は、数値管理だけでなく、現場で働く一人ひとりを守り、その努力を正当に評価するための仕組みでもあるのです。
まとめ
シェアードサービスの原価管理は、「誰が、どの部門の仕事に、どれだけの時間を使ったのか」という工数データから始まります。
TimeCrowdを活用すれば、日々の業務記録が自動的に原価管理の基礎データとなり、以下が実現できます。
- 部門別の真のコストを把握できる
- 仕切り率の妥当性を検証できる
- BPO検討の判断材料が得られる
- 繁忙期のリソース配分を最適化できる
- 依頼元部門への説明責任を果たせる
- 従業員の努力を正当に評価できる
企業ごとに、時間管理・タイムトラッキングに求める目的は異なります。私たちは導入時の丁寧なヒアリングを通じて、お客様固有の課題と真摯に向き合います。シェアードサービスの原価管理・工数管理に関心をお持ちの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
TimeCrowdは、Web制作・システム開発・コンサルティングといったプロジェクト型ビジネスを中心に、累計5,500社にご導入いただいています。最初の2週間は無料トライアルが可能ですので、この機会にぜひお試しください。